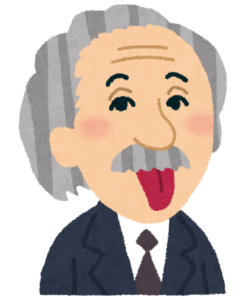
はいどうも、カワウソだよ。
『天才とバカは紙一重』ということわざがある。
世の中には、天才と呼ばれる人がいる。現代でいえば、将棋の藤井聡太さんや囲碁の仲邑菫さんが天才といわれるべき存在だろう。
しかし、そういった天才にはある共通点がある。
それが、変人だったり、どこか抜けていたりしているという点だ。
例えば、藤井聡太さんには、将棋のことを考えていたらどぶに落ちたとうエピソードがある。
何とも抜けているというか、そこもまた可愛いね。そういう一見おっちょこちょいなところが、かえって天才な感じをにおわせている。
彼だけでなく、多くの変人は、普通の人がしないようなおっちょこちょいをしでかしたり、普通ならできるようなことができなかったりする。今回は、そんな天才たちの奇癖・変人性について考えていこう。
目次
変人な天才たち
大学受験に失敗した天才・アインシュタイン
天才といわれて多くの人が思いつくのはアインシュタインじゃないかな。
物理を習得していない人にとって、相対性理論というのは良くわからない理論の代名詞と言えよう。
そんな相対性理論をほとんど一人で築き上げたアインシュタイン。(ただし一般相対性理論に関しては友人の数学者の力をかりた部分もある)
しかし、そんな天才アインシュタインは、なんと大学受験に失敗していたんだ。
アインシュタインはスイスの名門大学、チューリッヒ連邦工科大学を受験。そこで、数学と物理の試験はほぼ満点だったという。
しかし、総合点が足りず不合格となる。
彼の数学・物理力の高さに驚いた工科大の校長は、ギムナジウム(中学・高校のような教育機関)に通うことを条件に大学入学を許可した。
特定の科目がトップクラスによくできていたのに他の科目がてんでダメだったというのは、いかにも天才肌という感じだね。
さらに、大学入学後も、自分の興味ある科目だけ取り、そのため物理の実験では最低点を取った(一方、電気技術の講義は優秀な成績をとった)
ここだけ切り取ってみると、なんだかクズ大学生にも似たものを感じるね。
(参考サイト:ウィキペディア アインシュタイン)
『キミ、童貞?』と面接で質問したスティーブジョブズ
アップルの共通創業者、スティーブ・ジョブズにはいろいろとエピソードがある。
そんな中、個人的に最もぶっ飛んでいるなと思ったのはこのエピソードだ。
ジョブズは、ある面接で志願者にこう尋ねた。
『ねえ、君、いつ童貞卒業したの』
志願者は困惑し、「なんといったのですか」と尋ねる。
するとジョブズは「お前は童貞か?」といった。
さらに、LSDをヤッているかも尋ねた
いくらヒッピー出身だからといっても、童貞かどうかとか、薬物をやっているかとか面接できくわけがない。
もし今ジョブズが生きていたら、ポリティカルコレクトネスどころの話じゃない訴訟をおこされていただろうね。時代がよかったとしか言いようがない。
しかし、天才はそういうことを平気でやってのける。むしろ、そんな変なことをやっているから天才といわれたのかもしれない。
とにかく、ジョブズはぶっ飛んでいるといわざるを得ないよ。
滝の水を止めさせた棋士・加藤一二三
日本にも変人な天才がいる。その一人が、神武以来の天才と呼ばれた将棋棋士、加藤一二三だ。
今ではお茶目キャラ『ひふみん』として愛されているが、史上初の中学生プロ棋士、名人・王将・棋王・王位といったタイトルを獲得した天才だ。ネットがない時代というのも考慮すると、本当に天才中の天才だったと言えよう。
そして、この天才ひふみんもまた、エピソードに事欠かない人物である。
加藤一二三は、対局部屋の近くに人工の滝があることに気付き、止めさせたことがある。
ひふみんまつわるエピソードはたくさんあって、他にも、ネクタイが異様に長かったり、わざと入れ歯を入れなかったりしている。
食べ物にまつわるエピソードが特に多く、昼と夜とに同じメニューを頼む、東京の会館ではうな重を頼むのが定番となっている、などいろいろある。
存在そのものがネタになっている感があるけれど、加藤一二三さんもまた、変わり者の天才をしめす典型例であることには間違いないよ。
なぜ天才は変人なのか
目的のためなら手段をえらばない
では、なぜこのような天才は、分野にかかわらず変人なのだろうか。
一つの可能性として、目的のためなら手段を択ばないというのが考えられる。
上記した天才の中でいえば、特に加藤一二三さんがあてはまる。
滝の音がたとえ気になったとしても、普通はそれを止めようとしないだろう。
しかし、加藤はそれをした。
対局に集中するという目的のためならば、それに向かって一直線に行動するのが天才のなせる業だ。
逆に、ここで「滝を止めたら悪いしな……」とか考えると、そう配慮する分、脳のエネルギーを消費してしまう。
一切の妥協をしないからこそ最高のパフォーマンスを演出できるのだね。
天才は一つのことに特化し他の能力を犠牲にする
そしてもう一つ。
天才はいろんなことがまんべんなくできるのではなく、むしろ一つか二つのことに特化しすぎていて、他の能力はむしろ平均以下になるという可能性だ。
上の例だと、アインシュタインが最もそれに近いだろう。
脳細胞の多くが数学と物理の計算に支配された結果、他の能力が衰えてしまった。
興味のないことを覚えるのが苦手だったようで、自分の家の電話番号さえ覚えていなかったらしい。
このように、特定の領域に才能を特化させた天才例でいえば、ジミー大西さんがいい例だろう。
彼の絵は独特で、国際的にも評価されている。
しかし彼は漢字に弱く、運転免許の筆記試験に落ち続けた。
天才というほどではないが、僕が所属していたジャパン・メンサにもそのような人は結構いた。
メンサというのはIQが全人類の上位2%の人しか入れない組織なんだけれど、メンサ会員のうち2割から3割くらいは『天才かつ変人』だった。
メンサでは、頭脳ゲームやIQクイズをすることがある。その中で一番早くクイズに正解した人は距離感覚がない人で、しばしば人とぶつかっていた。
僕はお会いしたことないけれど、同じくメンサ会員でクイズ王のロザン宇治原さんは、絵がとてつもなく苦手で、彼の描いた動物の絵には恐怖さえ感じる。
このように、何かに特化した才能がある人は、他の能力が平均未満であると考えられるよ。
天才ではないまでも、僕もこの『能力の偏り』は強く体験している。
IQ的な、パターン認識の能力は人より優れているだろうけれど、空間認識の能力がてんでだめだ。
先日(この記事を書いた前日)も、英検の会場が駅から徒歩5分だったのに20分かかったよ。究極の方向音痴だよ。
こういった、能力の偏りがあるからこそ、多くの人ができないようなことができる一方で、誰でもできるようなことができない、天才性と変人性を併せ持つのではないかな。
まとめると
天才が変人たるゆえんは大きく2つ理由が存在すると考えられる。
一つは、目的のためなら手段をえらばないから。
もう一つは、能力が特定の分野に偏り、そのせいで別の分野の能力に欠陥が生じるから。
今回はここまでだよ。
皆さんは間違っても、初対面の人に「君、童貞?」などと聞かないようにしようね(^●ω●^)