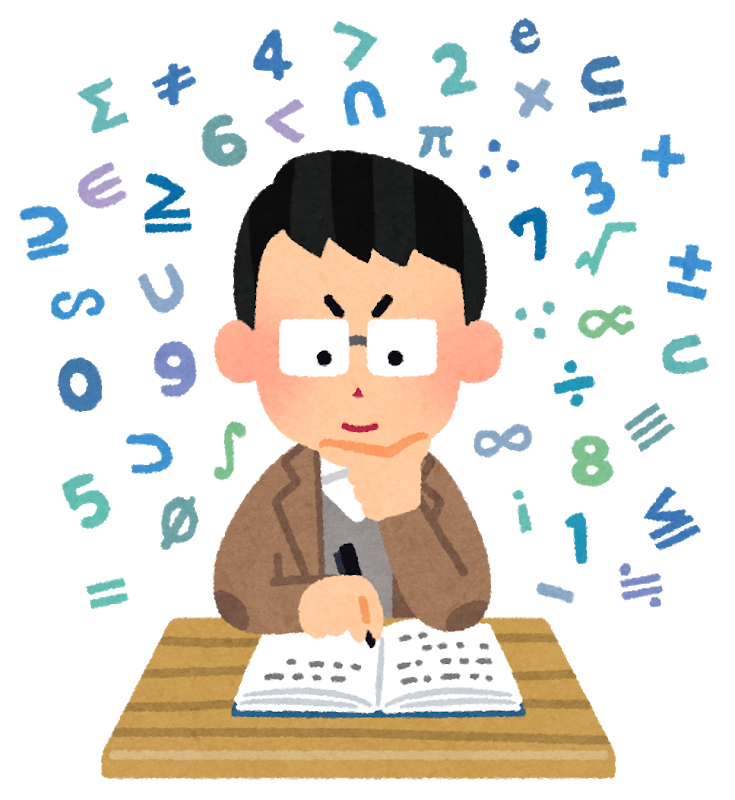
はいどうも、カワウソだよ。
2019年度第1回数検を受験したよ。
個人初めての受験だったけれど、その感想をかいていくよ。
目次
情報のほとんどない数検1級
社会人になって最もはやく衰えるのが数学の力だろう、理系学部出身でも、研究職についていない限り数学力はすぐに高校・中学レベルまで落ちてしまいかねない。
そう思い、先月僕は数検の1級を申し込んだ。
しかし、それからがちょっと大変だった。なんと、いくらネットを探しても、数検に関する情報がほとんどないんだ。
というのも、数検自体が思ったほどマイナーな試験だったんだ。
数検そのものを知っている人は多いだろう。2級以上を取得していれば、高認試験の数学が免除になる等メリットも大きい。
しかし、その受験者はあまりにも少ない。
例えば2017年の数検志願者数は約37万7000人。これは英検の約366万人や漢検の208万人とくらべて、文字通り桁違いに少ない。
(参考URL
https://www.su-gaku.net/suken/examination/data.php
https://www.eiken.or.jp/eiken/merit/situation/
https://www.kanken.or.jp/kanken/investigation/transition.html )
さらに1級に限定しては、志願者1394人、合格者に至っては74人だ。年に3回行われるから、一回あたり合格者は24.7人。あまりにも少なすぎるね。
受験者数がそこまで多くない上に、1級は難易度も高い(合格率6.5%)。そのため、1回あたりの合格者数は神社検定壱級よりも少ない。
それに輪をかけて情報流通の妨げになっているのが、数検の「検定上の注意」だ。
出題内容に関する事項を当協会の許可なくインターネットなどの不特定多数が観閲できるような所に掲載することをかたく禁じます
公益財団法人 日本数学検定協会
簡単に言うと、問題の内容を公開しちゃダメだってことだ。
そりゃあ、情報が出回らないのも当然だね。
以下、感想を書いていくけれども、数検さんに怒られるのが怖いから、問題内容については極力ふれないようにするよ。そのためわかりにくい文章になるとおもうけれど、勘弁してください。
さて、今回はそんな数検1級を受験した感想を書いていくよ。
一次試験感想
最初は一次試験。60分で7問を解く。
解答用紙には答えだけを書く形式で、だから大学入試と違って、過程が一切考慮されない。オールオアナッシングの世界で、一説には二次試験よりも合格点(7問中5問)を取るのが難しいようだよ。
そして、僕自身その難しさに圧倒された。
というのも、高次方程式に関する問題で計算がありえないくらいに大変だった。
おそらくもっと手早く計算する方法が間違いなくあるのだろうけれど、それをみつけられなかったよ。(1つの問題だったが解答は2か所あった。そのうち1つが解けなかった)
そしてもう一つ。最後の微分方程式に関する問題は、プラスマイナスを間違えて答えてしまったよ。
つまり、この時点で1.5問は減点されていることが判明している。これ以上間違えようがないということだね。
次回にむけて、また精進するよ。
二次試験感想
二次試験は120分で4問解くスタイル。
7問あって、うち2問は必修、のこりの5問から2題を選択して解く。
2題ある必須問題のうち、1問はおそらく満点だよ。ただし、もう一問、空間図形に関する問題は、自分の幾何的知識の不足があらわになったよ。
選択問題で選んだのは整数問題と統計問題。
まずは統計問題。
この分野は大学では習わず、一から独学だったのだけれど、過去問からパターンが読み取れたので勉強は楽だったよ。
とおもったら、まさかの本番でやらかした。
別に公式を忘れたとか、そういうのではない。
あまり具体的に言うのは禁忌だろうから言わないけれど、少なくとも僕の持っている過去問集(7回分が記載)には出題されていなかった検定がだされた。
その分(?)おそらく初心者でもギリギリ解ける程度の難易度になっていたから、なんとかなったと思っているよ。
整数問題に関しては、過去問以上にうまくいったと思っているよ。
(幾何系の問題が大の苦手だから、代数問題しか選択肢がなかったんだけれどね。)
とりあえず、自分の得意な分野に落とし込めて計算できた、としか言いようがないよ。
二次試験は6割正解で合格だそうだから、計算をしくじっていたり、記述が足りないと判断されたりしていない限りはなんとかなったのではないかと思っているよ。
今回はここまでだよ。
合否発表がされ次第、より詳しいことを書いていく予定だよ(^●ω●^)
コチラもオススメ!
小岩井ことりさんも入会!メンサ会員の特徴を現会員が考えてみた
元MENSA会員の僕が、『IQの高い人』について客観的に考える