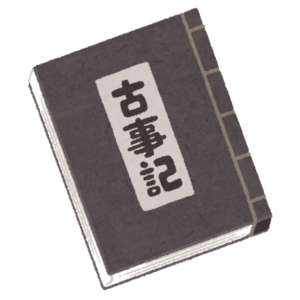
はいどうも、カワウソだよ。
来る11月28日、歴史能力検定を受験するよ。前回は日本史2級に合格したから、今回は日本史1級を受験するよ。
2級は教科書だけでなんとかなったのだけれど、1級はそれ以上に手ごわい。その対策として問題集を買ったんだけど、これがなんとも使いにくい。
今回は、そんな歴史能力検定問題集への不満を書くとともに、これからの勉強法を考えていくよ。
目次
歴史能力検定問題集への不満
『全級』問題集は需要がない
今回買ったのは、歴史能力検定2020年度全級問題集だ。そう、2020年度『すべての級』の問題が記載されている。
5級の歴史入門から、1級の日本史・世界史まで、すべての級が載ってある。
さて、ここで考えてみよう。すべての級の問題を見る必要がある人はいるだろうか。
答えは、否だ。
5級は、例えば、鎌倉はどこにあるでしょうとかの、小学生レベルの問題が出される。
一方で、1級日本史は、高校で習う範囲を超えている、少なくとも、手元の教科書や資料集だけでは答えられない問題もある。
少なくとも、5級と1級とを同時に読む需要はない。あるとしても、例えば5級と4級、2級と1級のように、レベルの近い2つの級を見比べるくらいだろう。
少なくとも、1級から5級まですべてを束ねて売る必要はどこにもないのではないかな。
各級問題集を売っていた過去
個別の級でうることは原理的に可能だ。そしてさらに言えば、この歴史能力検定の問題集、過去には級別で売られていた。
Amazonで検索した結果、どうも2013年度ごろまでは、1級世界史とか3級日本史とかのように、各級で販売されていた。過去5回分の問題がおさめられているようだ。
大学入試や高校入試では、過去数年分の問題を解くのが対策の定石だろう。それと同じように、同じ級の過去問を束で買えるのは非常にありがたい。
なぜ、全級束ねて、それも1年度だけで売るようになったんだろうか。売上の関係もあるのだろうけれど、正直不親切な改変だと思っているよ。
歴史能力検定、これからの勉強法
教科書・資料集だけでは足りない
不平をいったところで得点が上がるわけではない。受験を申し込んだ以上は勉強し、受からなければ受験料がもったいない。
で、現在の得点と、これから残り1か月間の勉強について書いていこう。
1級日本史では、合計30問出題される。そのうち20問はマーク式、8問は語句記述、2問は説明問題だ(2020年度の場合)。
それで、解いてみたところ、マーク問題の正解数は7問、語句記述問題は4問、説明問題は0問だった。配点にもよるけれど、このままだとおそらく30点とか40点とかどまりになる。
歴史能力検定は、60%が合格ラインだ。必要得点数でいえばかなり易しい。
しかし、現時点で正解率が4割にも達していない。これでは受かるはずもない。より勉強を加速させる必要がある。
解いた後に調べて気づいたのだけれど、30問中4問ほど、手持ちの教科書と資料集だけでは解けない問題があった。
さすが1級。仮に教科書と資料集が持ち込みだったとしても、満点正解をたたき出すのは不可能だ。
この対策として、一問一答集などの購入を検討しているよ。
また、間違えた問題も、ちゃんと記憶していれば解けた問題がいくつもある。問題数が少ないだけに、こういうところを落とすと非常に大きな失点となる。
残り1か月。教科書をあと3周して、知識をより多く、かつ歴史の流れにそって定着させていくよ。
今回はここまでだよ。
同じく歴史能力検定を受験される皆さん、一緒に頑張ろうね(^●ω●^)
2021年度歴史能力検定 日本史1級受験感想
難しいというより、わからない
11月28日、歴検の日本史1級を受験したよ。
はっきり言って、難しかった。より正しくいうと、わからなかった。
例えば論述問題。とある資料を読んで、時代背景などを書く問題があったのだけれど、まあできなかった。磐井の乱についての資料だったようで、その乱のこと自体は知っていたのだけれど、その資料が磐井の乱についてだとは全く気付かなかった。
マーク式ではかろうじて6割の正解を出したが、語句を書く問題では8問中1問しか正解せず、また2問ある論述も1問白紙だ。合格の可能性はない。
次回もまた受けるつもりだよ。今回の失敗を糧にして、次回こそは受かってみせるよ(^●ω●^)
こちらもオススメ!
歴史能力検定2級日本史に2か月で合格する、意識低い人のための勉強法【理系でも受かる】