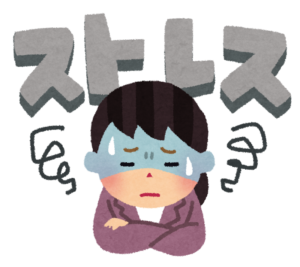
はいどうも、カワウソだよ。
Adoさんの「うっせぇわ」という曲が流行している。世の中の理不尽さ、そしてそれを直接訴えることができないを若者の窮屈感を発散させることで人気を得ている。僕もよく聞いているよ。
さて、この『うっせぇわ』のAdoさんは高校生だが、楽曲提供者のsyudoさんは大学を卒業している、すなわち社会人の年齢だと思われる。未成年のAdoさんが歌うにはやや大人向けの歌詞だが、もしかすると、syudouさんの実体験が関係しているのかもしれない。
さて、この『うっせぇわ』の歌詞。実は、高IQ界隈においても結構共通する部分がある。
今回は、『うっせぇわ』の歌詞をもとに、IQの高い人の悩みをひもといていこう。
目次
『うっせぇわ』と高IQ
『ちっちゃなころから優等生』という『失敗』
まず、『ちっちゃなころから優等生』という部分。これは一部の高知能者にも当てはまる。
なんとなく、天才は学校では落ちこぼれだというイメージがあるかもしれない。アインシュタインやエジソン、ジョブズなどの天才にそういう過去があったとされることからもそのことが言える。
ただし、天才的な能力のある人が全員そういうタイプかというと、そうではない。むしろ、IQが高かったり、人の気持ちを察する能力が高かったりした人の中には「小さくまとまってしまう」タイプも多い。
メンサ会員・東大卒の芸人、『田端藤本』の藤本さんもその一人だ。小学生のころ、校長先生の書いた字が間違っていることを指摘した結果、「大人はこれでええんや」と叱られた。そこから、「大人を指摘してはいけない」と学習してしまったようだ。
https://youtu.be/P2p8eT0bkSg
『優等生』をどうとらえるかにもよるけれど、それでいるためには理不尽なことを受け入れる必要がある。
別の育て方をされていたらナイフのような思考回路を持ち合わせていたかもしれないのに、『気づいたら大人になっていた』という、言ってしまえば『失敗』を体験する高IQ者は多いんだ。
『社会人じゃ当然のマナーです』を消化しきれない
上の学校生活もそうだけれど、社会においては理不尽なことが多い。社会人では当然のマナーと言われているものの中にも、なぜそれをする必要があるのか、理にかなった理由を求めることが難しいものがある。
そして、その理不尽さへの耐性は、おそらくIQの高い人の方が弱い。
ある特定の『理不尽』を個別で見た場合、それへの耐性はIQとそこまで関係はしないだろう。しかし、知能の高い人は、実感している理不尽の量が他と異なる。
一言でいえば、IQの平均的な人が受け流している『理不尽』についていちいち気になってしまうんだ。
例えば、将棋棋士の藤井聡太二冠は、「なぜ5分で理解できる授業を50分かけてやるのか」と先生に質問したそうだ。あるいは、宿題の必要性についても、「なぜ解ける問題をわざわざ宿題として課すのだろう」と思っていたそうだ。
あるいは、メンサ会員の宇治原史規さんもまた、上から指示されるのを嫌う。相方の菅さんが「●●でやってみよう」と提案しても、いちいち「なんで?」と質問していたという(菅広史・『京大少年』より)
上で、藤本さんが学生時代に「大人を指摘してはいけない」と学習してしまったというエピソードを書いたけれど、このことを氏が覚えていたということは、理不尽さを感じていたということのあらわれだろう。
まさに、高知能の人の脳内は『うっせぇわ』という言葉が響いているんだ。
なぜ高知能者の知能は『うっせぇわ』と共鳴するのか
不条理を『受け入れる自分』と『納得はしない自分』
僕は、高知能の人の悩みと『うっせぇわ』の歌詞がリンクしているのは偶然ではないと思っている。
現代人の精神は、実はIQの高い人の精神と共通する部分があるんだ。
「さとり世代」とか言われている平成生まれの人は、昭和生まれの人と比べると「権力に強い反抗を感じない」という傾向がある。
与党・自民党支持率は若者世代のほうが高いというのはわりと知られていることだけれど、政治だけでなく、ルールに従ういわゆる『優等生』タイプが増えた。少なくとも、窓ガラスを割ったり盗んだバイクで走り出す尾崎豊的な不良は大分少なくなったんじゃないだろうか。
しかし一方で、ルールやマナーを本当に心の底から受け入れているかというとそういうわけではない。
ツイッターを覗けばいやでもわかるけれど、常に世の中には理不尽が存在し、そしてそれについての愚痴もまたあふれている。『スカッとジャパン』なんていうテレビ番組もゴールデンタイムに放送されている。あるいは、20代の有名ユーチューバー31人が緊急事態宣言下で深夜に飲み会をしたと報道された。
若い世代に限ったことではないだろうけれど、理不尽なことが多すぎる。そして、一般的に年配の世代よりも少数者であることも関係して、上の世代以上にその理不尽さを「飲み込む」ことを強要されている。
このことからも、高IQ者の生きづらさと、若い世代の生きづらさは共通する点が多々あると考えられる。
だからこそ、若者の間で爆発的に流行った『うっせぇわ』が高IQの感じるモヤモヤと結びついているのだと思うよ。
多様な声遣いも高知能と共鳴する?
また、Adoさんは、この曲のパートごとで声を使い分けている。
「ちっちゃなころから優等生」というところはやや幼く、その次の「気づいたら大人になっていた」は大人っぽく、というように。注意して聞くと結構忙しい。
この多様な声の使い分けが『うっせぇわ』をより人気にしたのだろうけれど、この点は高知能者とも共通する部分がある。
もちろん、別に高IQの持ち主が声を使い分けているわけではない。ただ、いろんな『自分』が短い時間のなかで目まぐるしく入れ替わることがある。
多重人格とはちょっと違う。おそらく多くの人にとって、『人格』自体は変わらない。というより、その感覚が非常に薄い。ただ、その一つの人格がもつモノが変わる。
卑近な例でいえば、ある意見に対して賛成の立場をとっていたけれど、実は反対意見もすぐ思いつく。賛成か反対かは、自分自身というよりも周りが決める。相手がBといえば、Bである論拠を並べる自分がいて、Aの自分は封印される。
しかし、それそのもので何か抑圧された感はない。自分の脳内に異なる立場の自分がいるのは当然のことだとして、何の違和感も抱かない。
しかし、環境に左右されず、自分だけの時間となれば、時々過去に封印されていた「A」の自分が出てくる。それがちょうど、この「うっせぇわ」の声色と共鳴したよに感じたよ。
今回はここまでだよ(^●ω●^)
こちらもオススメ!