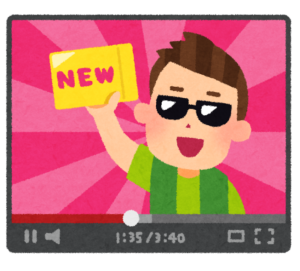
はいどうも、カワウソだよ。
この頃いろんな人がユーチューバーになっている。量だけでなく、ジャンルもいろいろと増えてきた。
その中で、教育系・勉強関係ユーチューバーというのも出てきている。
最も有名なのが、ダンサーの中田敦彦さん主催のYouTube大学だ。あるいは、広い意味で言えばメンタリストのチャンネルもここに当てはまるだろう。
一般的に、YouTuberの登録者数はおおければ多い方がいい。別にそれが絶対ではないのだけれど、どうも登録者数や再生回数の多寡がひとつのステータスになっているようだ。
確かに、バラエティ系、エンタメ系のユーチューバーはそうだろう。登録者数100万人を超えているユーチューバーはどれも面白い。面白いチャンネルは自然と登録数が増えるし、登録者数の伸びがいまいちであれば、それは視聴者にとって面白くないということの表れだろう。
しかし、こと教育・勉強系の動画に限って言えばそれは正しいとは言えない。登録者数や再生回数が多いからと言って、その質が保証されているわけではない。
むしろ、個人的には、登録者数が200万を超える教育系チャンネルには基本的にちょっと注意した方がいいとさえ思っている。
今回は、教育・勉強・その他ためになる系のユーチューブチャンネルと、その質の関係についてみていこう。
目次
YouTubeは「質が高いから大人気」とは限らない
デマを垂れ流す『ナンバーワン教育系YouTuber』
上でも示したけれど、おそらく教育系・あるいは教養関係のユーチューバーというジャンルで最も有名な一人が、中田敦彦さんだろう。登録者数は300万を超える、超人気ユーチューバーと言って過言ではない。
そんな中田さん、日本史や世界史だけでなく、文学から漫画、本当に多種多様なジャンルを扱っているのだけれど、その間違いの多さもたびたび指摘されている。
例えば、ヴィーガンについての動画では、農業ジャーナリストの人に「明らかな間違い」だと批判されている。
「完全なデマ」 中田敦彦のヴィーガン解説動画を専門家が痛烈批判
中田敦彦氏が拡散する「飢餓を生むのは畜産業(家畜が食べる穀物のせいで)8億2千万人が飢えて死んでいるのが現実」は完全なデマ。その人数は飢死でなく、国連FAOによる栄養不足人口(PoU)の推定値。その計算式の中で家畜はむしろ重要な栄養源。ヴィーガン本の畜産ヘイトネタを検証なく垂流し。要訂正→ pic.twitter.com/KZQz1hzxjM
— 農業と食料の専門家/浅川芳裕 (@yoshiasakawa) January 13, 2021
中田さんは読んだ本の内容を紹介しているのだけれど、元の本で「8億人が飢えで苦しむ」という表現だったところを「8億人が飢えで死んでいる」というような、大きな言い間違いもしている。これは、紹介された本の著者も複雑な思いをするだろう。
このレベルの人が、『ナンバーワン知識系ユーチューバー』なのが現実だ。
数検1級最年少合格者が学んだユーチューバーのチャンネル登録者数は65万
では、中田さんよりも登録者数の低い教育系ユーチューバーの動画の質が彼のより悪いかというと、そんなことはない。
例えば、「予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」」というチャンネルがある(略称・ヨビノリ)。この記事を書いている時点で、登録者数は65万人だ。
解説している「たくみ」さんは、東大院出身、「大学生の理系離れ」を解消するために、大学で学ぶ数学や物理を、予備校のように「わかりやすい」授業で解説している。僕も学部生時代は大変お世話になった。
そんな「ヨビノリ」、数検1級最年少合格者が学んだチャンネルでもある。
なんと、合格者の安藤さんは、ヨビノリなどのYoutubeを見て数学や物理を勉強したという。
このヨビノリさんのチャンネル登録者数は65万。めちゃくちゃすごいんだけど、質が高い故に「なんでこのチャンネルの登録者数が200万ないんだろう」と思っている。デマや間違いも僕の記憶する限り見たことがない。
日本一の教育者は登録者数100万達成までに8年かかった
また、
僕の知る限り、授業系のチャンネルで登録者数100万を超えているのは「とある男が授業をしてみた」だ。投稿者は葉一(はいち)さん。
でも、このチャンネルの登録者数が100万人を突破するのに8年かかった。
では、この動画が中田敦彦さんの動画よりも劣っているかというと、決してそういうわけではない。
むしろ、日本一学生の役に立っているチャンネルといっても過言ではない。
例えば上の動画なのだけれど、コメント欄で、はいちさんの動画をずっと見ていたおかげで、問題を見た瞬間に補助で書くべき図が見えたとコメントしている人がいた。
ほかにも、高校合格報告をコメントでしている人がたくさんいた。おそらく、日本で一番小中学生の学力向上に寄与した先生だろう。
そんな彼なら、登録者数100万も当然だ。むしろ8年かかったというのが意外なほどハイクオリティな動画を上げ続けている。
視聴者の層が違うから単純比較はできないのだけれど、少なくとも教育系のチャンネルにおいては、登録者数の大小が必ずしも質の高低を左右しているわけではないようだよ。
なぜ教育系ユーチューバーの質と人気は比例しないのか
初心者の説明する「わかりやすさ」には要注意
なぜ、教育系ユーチューバーの質と人気は完全には比例しないのだろうか。
その理由の一つは明確だ。中田敦彦さんが扱っている動画のジャンルが広いんだ。
「約束のネバーランド」と「お金の大学」を同じチャンネルで取り扱っているということからも、その幅の広さがうかがえるね。
でも、それは質の面でみるとどうなんだろう?
中田さんは、本や漫画を見て、それをまとめて動画にしている。そして、その本はたいていの場合、多くて2、3冊だ。
いくら中田さんがもともと博識だったからといっても、いろんなジャンルを週にいくつも扱っていれば、一つ一つの理解は弱まる。中には中田さん自身初めて触れるジャンルもあるだろう。
ここが問題だ。
中田さんは「新書を2冊読んで得たものを解説」している。別に、その分野に詳しいわけではない。トーク力は芸人生活で培ったものだろうけれど、話す内容自体は、時間さえあれば素人でも1日2日あればできるものが多い。
一方で、後者、葉一さんは教育・ヨビノリたくみさんは物理を大学(あるいは院)で学んでいる。こちらは、素人がやろうと思ってもすぐには始められないところがあるだろう。
同じ「わかりやすい」動画を投稿していても、背景にこれだけの差があるんだから、当然投稿する質に差が出ているのも仕方がないよね。
間違いだらけの解説はすぐ人気になりやすい
また、中田さんの動画の特徴として「間違いが多い」というのがあるのだけれど、これもまた、再生回数が多いことの原因となっているかもしれない。
というのも、一般的に、間違っている内容の方が正しい内容よりも、より広がりやすいんだ。
嘘が拡散する速度は事実よりも20倍はやいというデータもあるようだけれど、まさに中田さんの成長はそれを物語っている。
というのも、中田さんの動画に間違いが発見されたとき、TwitterなどのSNSでそのことが指摘される。あるいは、ニュースになる。
ただ、その場合、SNSだと「どんな動画だろう?」と興味をもって元ネタを見に行く人が一定数いるし、ニュース記事であれば「この動画でデマが流された」という引用元の動画を掲載する必要がある。その結果、どんどん話題になり、再生回数や登録者数が増える。
一方で、正しい動画はあまり広まることがない。基本的に「正しい」内容はつまらないことが多いからだ。
この「嘘ほど金になる」「間違っていればいるほど人気になる」という現実をグーグルなどがいろいろ対応しているんだけど、今のところそれがいまだに現実のようだ。
これはエンタメ系のジャンルならまだ被害は小さいのだけれど、教育・教養系の動画に関しては、インフルエンサーの人ほどこの事実をしっかり受け止める必要があると思うよ。
今回はここまでだよ(^●ω●^)