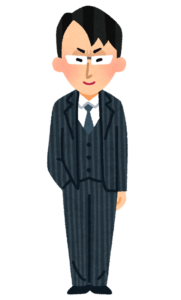
はいどうも、カワウソだよ。
世の中には、「正論(をいう人)は嫌われる」という傾向があるようだ。
一見、これは理不尽だ。正しいことを言った人が敬遠されるというのは、物事を解決するにあたってよくないように思える。
しかし、よくよく考えてみると、正論をいうことが必ずしもいいことではない、いわば『正論の限界』みたいなものが見えてくるよ。
今回は、なぜ正論が嫌われるのか、その理由を考えていこう。
目次
正論は「正しい」わけではない
まず、正直に言うと、正論など存在しないんだ。だれにとっても正しい意見というのは存在しない、見せかけの『正論』とでもいうべきものなんだ。
たとえばなんだけれど、地球温暖化についても、温室効果ガスが原因だと証明されたわけではない。「こういう数値に基づいて計算するとこうですよね」とあるだけで、これを「嘘っぱちだ」と思っている人には響かない。
国連とか大学とかの期間がいろいろ調査していると思うけれど、そのすべての機関がグルになってフェイクニュースを作りあげている可能性も否定できないんだ。
もちろん、環境の論文の嘘を暴くのは容易なことではない。正直嘘をつくメリットもあまりない。しかし、それが嘘でないと証明するのもまた難しいことだ。
本題とは少し離れるけれど、嘘が嘘であることの証明がいかに難しいか、別の例をあげて考えてみよう。
小池百合子・東京都知事の学歴詐称問題が話題となったことがあるけれど、カイロ大学が「小池は当大学の卒業生ではない」と主張することはできない。そもそも、彼女が大学を卒業したとされる年から40年以上たって浮上したのだから、仮にそれが嘘だったとすれば、彼女は少なくとも40年もの間、嘘をかくしとおせたことになる。彼女が学歴詐称していたかは、知事の態度とか、あるいはいろいろな記事の情報に頼るしかない。しかし、仮にどれだけ怪しくても「かなり黒に近いグレー」にしかならない。
もっとファンタジックな、しかし哲学的な疑問として「世界誕生5分前仮説」というのがある。これは、この世界ができたのは5秒前で、僕たちが持っている記憶や情報は、すべて神様に植え付けられたものだという仮説だ。
一見、この世界が5分前に誕生したというのは信じがたいが、これを否定することは、今のところできない。
いわゆる「悪魔の証明」というやつなんだけれど、多くの人はこの存在をあえて無視している。考えてしまうと、それこそまともな生活ができなくなってしまう。
正論の多くは、この「悪魔の証明」よりも低次元のところで否定することができる。例えば、「人間はいつか死ぬ」という正しい主張も、正確に言えばその正しさを保証できない。もしかしたら実は1000年くらい生きている人がいるかもしれない。実はその人は身長が1ナノメートルしかなくて、人類に発見されていないだけかもしれない。
あるいは、今まで生きている中ではいなかったとしても、将来不老不死の人間が誕生しないとも限らない。
そういうことを考えると、その正しさを証明できる「正論」というのは、たぶん存在しない。
僕自身『科学的に正しい』という言葉を使っているのだけれど、これは「統計的には、99%の確率でこうである」とかいう意味であって、100%正しいとは言えない。これが、正論の限界とでもいうべきところじゃないかな。
正論は「正しい方向の論」ではない
本質的でない『正論』をいわれてもどうしようもない
また、得てして、関係あるようで本質的でない正論を振りかざす人もいる。こういう『正論』にしたがったところで、いい結果を生むとは限らない
例えば、僕はこの記事のタイトルにおいて「メンサ会員」という言葉を付け加えている。でも、これって『正論』の面からすると『正しくない』かもしれない。IQの高低は議論の内容と関係ないしね。
「メンサ会員かどうかって、話の内容に関係ないですよね?」という指摘は、まさに正論だ。それを否定することはできない。事実、メンサ会員とかIQとかに関連させた内容は一切かいていない。だから、メンサと書くのはよくないことかもしれない。しかし、この『正論』は、はっきり言って意味がない。
僕にとって大切なのは、この記事が多くの人に読まれるか否かだ。そして、その点に関して言えば、おそらく『メンサ会員』という言葉を足しておけばちょっと希少性が出て、読む人が増えると思われる。
テレビ番組やユーチューブチャンネルでも、「この内容でこのタイトルなのはおかしくないか?」というのがしばしばある。「その議論、東大生使う必要ある?」とか、「このタイトルでこの内容はおかしいだろ」と思うことはしばしばある。
でもこういう場合、『必要性がない』という正論と、『こっちのほうが売れる』という正論の2種類が存在する。そして、がビジネスでやっている以上、いかにして売れるかが大事になってくる。行き過ぎたタイトル詐欺がよくないのも、別に『必要ない』という正論が勝っているわけではなくて、信用がなくなって読まれなくなるからだ。
他の例をあげてみよう。
髪の毛が薄くなった人に「ワカメとか頭皮マッサージとか、やってみようかな」と相談されて、「わかめとかマッサージとか、意味ないですよ」という人がいるとする。これは正論ではあるけれど、嫌われる正論だろう。(ちなみにこれは、Yahoo!知恵袋で正論が嫌われることについての質問に対するアンサーであったものだ)
しかし、この人は、正論を言ったから嫌われるのではない。『嫌われる正論』を言っているから嫌われるんじゃないかと思う。
この相談者は、なぜこの相談をしたのか、考えてみよう。おそらく、「ハゲはかっこ悪い」と思っているはずだ。で、そこに「●●は効果はない」とだけいったところで、なんの進展もない。
では、正論は必ず進展がないというかというと、そういうわけでもない。たとえば、「AGA治療のほうが効果的だ」というのもまた正論だろう。正論に基づいて、そちらを勧めることだってできる。
あるいは、「ハゲがかっこ悪いとは限らない」というのもまた正論だ。この質問者に「なぜハゲをなおしたいのですか」と聞くと、おそらく「ハゲはかっこ悪いからだ」という答えが返ってくる。その場合、「いや、そうとも限らないですよ」といって、ハゲのスターをあげればいい。
それで、「むしろバーコードだと気になってしまうから、いっそのことつるっぱげにするのはどうでしょう」という新案を作ることだってできる。同じ正論でも、一方は人を傷つけ、他方ではよりよい解決に向かわせる。そして、嫌われる『正論』論者はたいていの場合前者ではないかな。
「なぜ正論は嫌われるのか」の答えは、「正論の中でも、嫌われる上に進展のない正論を言うから」ということになると思うよ。
正論の限界
正論はしょせん感情論
多くの人が誤解していると思うのだけれど、少なくとも現実における議論において、正論は多くの場合感情論なんだ。
正論と感情論は、あたかも正反対のように見える。しかし、どうも掘り下げていくと、何かの議題において正論を作ろうとすると、どうしても自分の感情に頼ってしまうところがある。
一般的に、ある議論において完全に賛成とか、完全に反対とかというのはほぼほぼ起こりえない。
国政選挙がその一例だ。いろんな公約をマニフェストとして掲げて、その中で自分が重視するもの、あるいはこれまでの実績なども考慮して投票先を決める。
その際、すべてのマニフェストや実績を評価する人は少ない。「●●党のこういうところはダメだが、ここは評価する」といった具合だ(そもそも真面目に公約を見ている人がどれだけいるかは分からないが)
この場合、例えば「子育て支援」と「年金問題」のどちらが重要かなんて、人によって違う。学校のテストでは、問1は3点、問い2は2点というように配点が決まっていたけれど、選挙においては、有権者がどの公約に何点配点するかは人それぞれだ。
選挙以外でも同じだ。たいていの場合、メリットとデメリットとがある。そして、そのメリット・デメリットがそれぞれどのくらいの大きさを持っているかは人による。自分にとって些末なことがある人にとってはかなり大事かもしれないのに、それを無視・軽視してしまっている可能性を否めないでいる。
ネットで使われる言葉で「それ、あなたの感想ですよね?」というのがあるけれど、どんな主張にも必ず自分の感想や感情が入っている。
正論を絶対視する人は、そういう、正論の持つ感情的な面に気付いていないんじゃないかな。
今回はここまでだよ。
正論は、決して正しい論ではないし、それが正しくても、正しい方向に向かう論とは限らない。また、一般的な議論においては、正論は感情的な面を否定できない。そういう点で、「正論はただしくない」ということがいえるのではないかな(^●ω●^)
こちらもオススメ!